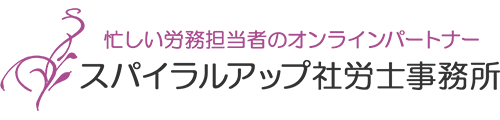【コラム】あらためて確認!! 年次有給休暇

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です。
経営者・労務担当者の皆さまが日々の労務管理の中で扱うことの多い年次有給休暇(以下、有休と呼びます)について、あらためて確認してみましょう。
◆年次有給休暇について
▶︎目的
・自身や家族が病気をした時のためなど、やむを得ない欠勤により賃金控除される事を回避するために利用する印象が強い有休ですが、本来の目的は「リフレッシュのため」です。
・労働者が心身の疲労を回復し明日への活力と創造力を養い、ゆとりある勤労者生活を実現するための制度です。
▶︎基本的なルール
・雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日付与されます。
・その後については、継続勤務1年ごとに前1年間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して与えます。
・事業場の業種、規模に関わらず、また、パート、アルバイト等の呼称に関わらず、外国人技能実習生も含め、全ての事業場の労働者に適用されます。


▶︎注意ポイント
・原則として、使用者は労働者からの有休取得の請求を断ることはできません。
・取得理由を問う必要もありません。
・時季変更権により取得する日の変更を命じることができるのは、事業の正常な運営に支障をきたす場合に限られます。
《例》同じ期間に多数の労働者が休暇を希望したため、全員の希望を叶えると事業の正常な運営ができない場合 等
・使用者は、法定の有休付与日数が10 日以上の労働者に対して、年5日以上取得させる義務を負っています。
・有休を取得した日は、出勤したものとみなします。
・有休を取得したことにより、不利益な取り扱いをしてはいけません。
《例》賃金を控除する、精皆勤手当を不支給にする、賞与の査定を不利にする 等
・有休の取得意欲を低下させるような取り扱いも禁止されています
《例》有休を取得しなかった人のボーナスを増やす 等
・有休の時効は2年です。
・有休の取得順序に法的な定めはありません。「新しく付与された分から取得」と就業規則で定めることも可能です。一般的な「繰越分から順に取得」の場合と比べて、有休消化率は高くなる傾向にあります。
・継続雇用されている途中で雇用形態が変わっても、すでに付与された有休は引き継がれます。
《例》パート→正社員、正社員→嘱託社員
・計画的付与、時間単位で付与する場合は、労使協定を締結する必要があります。

◆運用上迷いやすいポイント
▶︎短時間労働者
・1日の所定労働時間が労働契約で決まっている場合は、その時間分が有休となります。
※通常の賃金が支払われることが多いです。
《例1》所定労働が1日5時間 、時給1000円
→ @1,000×5時間=5,000円
《例2》所定労働が「月曜6時間、水曜3時間、金曜7時間」、時給1000円
→ 月曜なら @1,000×6時間=6,000円、水曜なら @1,000×3時間=3,000円
・1日の所定労働時間が決まっていない場合は、賃金を「時給×所定労働時間」で算出できないため、平均賃金を使うことが多いです。
▶︎公休日に有休を取得できる?
・有休とは所定労働日の労働を免除することですので、そもそも労働義務のない休日に有休を取得することはできません。
▶︎有休の買取
・買取は原則禁止ですが、時効消滅する年休や退職時の未消化年休は例外的に認められます。ただし、リフレッシュという本来の目的から外れるため、おすすめはしません。
▶︎退職時に未使用の年次有給休暇がある場合
・労働者からの請求がなければ、取得させる必要はありません。
・労働者は退職日後に有休を取得できません。(労働義務が消滅するため)
・退職までに消化しきれなかった有休の買取を労働者が求めた場合、使用者は応ずることも拒否することも可能です。(退職時の有休買取は義務ではありません)
▶︎産前産後休業・育児休業中の取り扱い
・産前産後休業中、育児休業中は出勤したものとみなし、復職後は継続勤務年数に応じた日数を付与します。
▶︎前倒し付与
・年次有給休暇の一部を前倒し付与した場合、翌年以降は最初に付与した日を基準日とします。
《例》令和6年4月1日入社の時点で5日付与、6か月経過後(10月1日)に残りの5日を付与した場合の基準日は、4月1日です。令和7年4月1日に11日付与する必要があります。
年次有給休暇については、こちらでもおしゃべりしています。
ぜひ参考になさってくださいね!
◆有休管理簿をつけていますか?
令和4年の有休の取得率は62.1%となり過去最高となりましたが、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和6年8月2日閣議決定)では、令和10年までに有休の取得率を70%以上とすることが、政府の目標に掲げられています。

そうした流れのなかで、会社が有休の取得義務を果たしているかどうかを労働局にチェックされる機会が増えています。
労働基準監督署の調査時はもちろんのこと、助成金の申請時に「有休管理簿の写しを提出してください」と言われた事例もあるようです。

これからは、有休取得を織り込んで人員配置や人件費を考える必要がありますね。
年次有給休暇の管理に不安があるときは、ぜひ社会保険労務士にご相談ください!
**********************
みつける・なおす・つよくする
選ばれる会社づくりをお手伝いします。